「外国製のおやつって大丈夫かな?」
「オーガニックってよく聞くけど、どこまで信頼していいの?」
日本で慣れ親しんでいるような基準とはちょっと違うかもしれませんが、ドイツやEUのオーガニック認証は、子どもにあげたい“安心できるおやつ”を選ぶうえで、とても頼りになる目印なんです。
この記事では、
- EUとドイツのオーガニック認証ってどういうもの?
- どんな点がチェックされているの?
- 日本の有機基準と比べて何が違うの?
- それが子どものおやつ選びにどう役立つの?
といった疑問に、わかりやすく答えていきます。
1. EUおよびドイツのオーガニック認証ってなに?
EUのオーガニック認証マーク

この緑の葉っぱマークをご覧ください。
これが EUオーガニック認証 のシンボルです。
EU全体で統一ルールが決められていて、
- 原材料の95%以上がオーガニック由来、残り5%についても厳格に定められた条件のみ使用可
- 化学合成農薬や化学肥料は原則使えない。ただし、例外的に使用が認められる場合は欧州委員会が許可したもののみ
- 遺伝子組換えはNG
- 動物はちゃんと放牧できる環境で育てる
といったことが守られています。
加えて、製品には認証を行った「監督機関のコード番号」や「原材料の産地(EU農業 or 非EU農業など)」の表示が義務づけられています。つまり「自然にできるだけ近い方法」で作られている食品の証なんです。
ドイツのBIO SIEGEL(ビオ・ジーゲル)

そして、ドイツ国内でよく見かけるのが 六角形の緑色マーク「BIO SIEGEL(ビオ・ジーゲル)」。
このマークは2001年に導入されたドイツ政府公式のオーガニック認証で、EU統一ロゴが義務化される前から存在していました。
Bio-Siegel は、EUのオーガニック規則に沿った製品に付けられるため、結果的にEU基準を満たした製品に付与される公式マークとして機能しています。
- EUオーガニック認証:EU加盟国共通の基準
- BIO SIEGEL:EU認証をクリアした上で、ドイツ市場向けに「この商品は有機ですよ」と示す政府公式マーク
つまりBIO SIEGELは、「EU基準を満たしている」+「ドイツで公的に保証されている」という二重の安心材料になるんです。
ちなみに… 食品が対象なので、化粧品や医薬品にはこの認証マークは適用されません。
2. 審査では具体的に何がチェックされる?
「オーガニック」の認証には、ファームから加工、輸送に至るまで、幅広い審査があります。ここでは特に詳しく見ていきましょう。
① 使用できる肥料や添加物は、欧州委員会が認可したものだけ
EUのオーガニック認証では、肥料や添加物など、有機で使えるものは欧州委員会が認めた限られたものだけなんです。このリストは定期的に見直されていて、最新の添加物リストはImplementing Regulation (EU) 2025/973〔有機加工食品などで使用できる添加物・加工助剤等のリスト〕に載っています(2025年9月現在)。
こうした制限のおかげで、オーガニック食品は化学的に合成された一般的な肥料や農薬を大幅に減らして作られていて、より自然に近い方法で育てられていることが保証されるんですね。
出典:
- Regulation (EU) 2018/848, Article 24 / Annex II, Part IV(有機生産で許可される物質等の原則)
- Commission Implementing Regulation (EU) 2025/973(有機加工食品で許可される添加物等)
② 動物福祉ってどんなこと?鶏の例でチェック
EUのオーガニック認証では、動物たちが「自然な行動ができる環境」で暮らせることがとても大切にされています。たとえば鶏の場合、鶏舎の作り方や飼育密度、設備、屋外へのアクセスまで、細かい基準がしっかり定められています。
具体的には、
- すべての鶏が簡単に屋外に出られるように鶏舎を設計する
- 屋外スペースはすべての鶏がアクセスでき、魅力的な環境にする
- 鶏舎には止まり木(1羽あたり10cm以上)、巣箱、つつき床材などを置いて、鶏が自然な行動をとれるようにする
- 室内・屋外の最低面積(例:1㎡あたり最大10羽など)や、屋外運動場の草地化もきちんと規定
こうしたルールは、単なる「おすすめ」ではなく、有機認証を受けるために守らなければならない基準なのです。
出典:
③ 流通の全過程もちゃんと管理されています
有機製品は、農場から最終的に消費者に届くまでの流通工程でも、厳格な管理が求められています。
具体的には、有機製品と非有機製品が混ざらないように、輸送容器や車両の封印や表示、清掃手順、輸送書類の管理、在庫の識別・記録保持などが決められています。
これらのルールは、EU内で有機認証を受けている生産者や加工業者、流通業者に適用されるので、「栽培だけでなく、EU内で消費者に届くまで」一貫してオーガニックの管理が行われているんです。
出典:
3. EU基準をクリアした、さらに一歩進んだオーガニック認証
EUの有機農業規則を遵守しつつ、より厳しい基準を設けている団体認証がドイツには複数あります。
代表的なのが以下の3つです:
Demeter(1928年創立)

Demeter(デメター)は、1928年に設立された、世界で最も歴史のあるオーガニック認証団体です。
EUオーガニック基準よりもさらに厳しい独自基準をもち、100%有機で、思想家ルドルフ・シュタイナーの提唱した「バイオダイナミック農法」に基づいて誕生しました。
農場全体をひとつの生命体ととらえ、土・植物・動物・人間が調和して生き生きと循環することを大切にしています。
バイオダイナミック農法の主な特徴は、
- 月や星のリズムに合わせて種まきや収穫を行う
- ハーブや鉱物などを使った特別な堆肥(プレパラート)で土を活性化
- 動物のふんや、収穫後に出る作物の残りなどを活かして、農場の中で肥料や飼料を循環・自給する
こうした農法を通じて、生物多様性や動物福祉にも高い基準で配慮されています。
さらにデメターは、社会的責任にも力を入れています。
民族や性別にかかわらず平等な機会を提供し、健康で安全な労働環境を守ることが、バイオダイナミック生産の基本原則に含まれています。
農業にかかわる人々を尊重し、自分たちの力で続けていけるように、支え合うことも大切にしているのです。
Bioland(1971年創立)

ドイツでは、スーパーで「Bioland」のマークをよく見かけます。
Bioland(ビオラント)は、ドイツと南チロル(イタリア最北部)にある約9,000の有機農家・養蜂家・ワイン農家が集まってつくっている団体なんです。
農家だけでなく、加工・流通・飲食などの分野で働くパートナー企業も1,400以上いて、畑から食卓まで、ものづくりの全体を支えています。
Biolandが目指しているのは、自然と調和した農業を次の世代へつなぐこと。
ただ有機農産物をつくるだけでなく、環境や地域、人とのつながりも大切にしています。
オーガニックの基本である、化学合成農薬や化学肥料は使わないこと、遺伝子組み換えを使わないこと以外に、次のような特徴があります。
- 生き物の多様性を守る:いろいろな植物や動物が暮らせる環境づくり
- 土と水を大切にする:化学肥料に頼らず、土を元気に育てる
- 動物福祉を大切にする:放牧や広いスペースで、ストレスなく育てる
- 地域に根ざす:できるだけ地域の中で生産・販売して、輸送を減らす
- 公平な経済をめざす:農家やパートナー企業が続けられる、信頼ある関係づくり
Biolandは、地域に根ざした小さな農家たちが力を合わせてブランドを守る、そんな団体です。
Naturland(1982年創設)

Naturland(ナトゥアラント)は、世界60か国で、約12万8,000人の農家が参加している国際的なオーガニック認証団体です。
ドイツ以外の国では、小規模農家が協同組合や生産者グループとしてまとまり、力を合わせて活動しています。
世界で合計75万ヘクタールの農地を管理していて、紅茶やコーヒーのほか、バナナ、パイナップル、カカオ、さとうきび、スパイス、オリーブ、エビ、サーモンなど、さまざまな農産物や水産物がNaturlandの認証を受けています。
動物福祉や生物多様性だけでなく、「人にも自然にもやさしい農業」を大切にしていて、社会的責任にも力を入れています。
たとえば…
- 児童労働がある地域では、子どもたちが学校に通えて、健康や成長を妨げられないように配慮
- 労働安全や事故防止の設備を整え、特に作業負荷が高くなりがちな小規模農家をサポート
- 最低賃金の遵守や、年金・健康保険への拠出もしっかりチェック
こうした社会的ガイドラインは、すべてのNaturland認定生産者に適用されます。農家だけでなく、養蜂家、漁師、昆虫の飼育者、そして加工業者やトレーダーも守る必要があります。
Naturlandは、世界中の農家と働く人、地域や子どもたちみんなにやさしい農業のしくみを大切にしているんですね
これらの団体認証は、EUの基準を満たしたうえで、自然、地域や生き物、そして働く人々への配慮がしっかりされていることの目印でもあります。
4. 日本のオーガニック基準と比べるとどう?
日本にも「有機JASマーク」がありますね。
基本的にはEUと同じで、農薬や化学肥料は制限され、遺伝子組換えは使われません。
でも少し違いもあります。
日本の有機JASは、どちらかというと農産物や畜産物そのものにフォーカスしていて、野菜や穀物、肉や卵がどう作られているかを重視しています。加工食品についても規定はありますが、EUほど細かく包括的ではありません。
一方でEUのオーガニック認証は、原材料だけでなく加工食品の添加物や加工方法まで細かく規定しています。だから「同じオーガニック」といっても、中身のルールは少し違うんですね。
さらに、ドイツ独自の団体認証では、EU基準をクリアしたうえで、動物福祉や環境・地域・持続可能性への配慮に、より深く踏み込んでいます。
どの国の認証制度も、時と共により良くなるよう更新されています。公式にEUの認証と互換性が認められている日本の有機JASも、農産物や加工品の安全・品質を守るために十分な基準が整っているので、安心しておやつ選びの参考にできますよ。
5. 子どものおやつ選びに役立つポイント
じゃあ実際、おやつを選ぶときにどう役立つの?と思いますよね。
- 余計な農薬や添加物を減らせる
- 作り手の考え方や姿勢が見える
- 農作物の育て方・加工方法・添加物の使い方など、できるだけ自然な形を守って作られている
もちろん「オーガニック=絶対安全」ではありませんが、より安心して選べる基準として助けになりますね。
つまり、オーガニックを選ぶことは「おいしいおやつを楽しむ」だけでなく、健康・環境・社会まで意識した選び方になるんです。
6. まとめ:EU・ドイツオーガニックの強み
- EUロゴがあることで、認証内容が一目でわかる透明性がある
- 農場から加工・流通まで、食品が作られる全過程で細かくチェックされている
- より深い自然環境や動物福祉への配慮がされている
だからこそ、子どものおやつ選びで「安心できる理由」になるんです。
ただ美味しいだけじゃなく、背景にこうした努力があることを知ると、ちょっと選ぶのが楽しくなりますよね。
さらに嬉しいのは、オーガニックを選ぶことで 自分たちの健康だけでなく、動物の福祉や、農業・加工に携わる人々を応援することにもつながること。
おいしいおやつを楽しみながら、ちょっとだけ世界を良くする選択ができる——こんな楽しみ方も素敵ですよね。


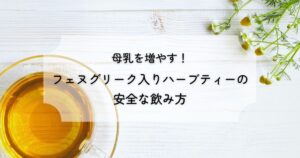

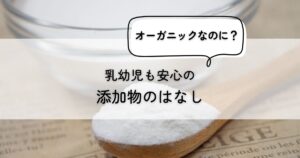


コメント